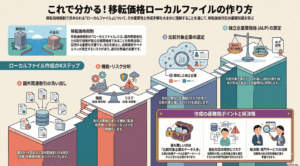解説&用語集【2025年11月更新】

国際税務(移転価格)関連の用語について定義及び概要をまとめたものです。なお、本記事はあくまでも筆者の執筆や研究の一環で作成したメモに基づく参考情報であり内容の正確性については原文・原典をご確認ください。また、今後に継続的に新出・既出を問わず用語集を更新していく予定ですので、掲載を希望する用語や内容修正のご提案等がございましたら弊社までお知らせください。
国際税務・移転価格用語集
International Tax & Transfer Pricing Glossary (No.1-200)
該当する用語が見つかりません
BEPS
BEPSとは、税源浸食と利益移転を表す「Base Erosion and Profit Shifting」の頭文字を取った略語。多国籍企業が国際課税制度の仕組みを活用し、グループ内取引の特性や法的解釈を巧妙に操作することで、いずれの国・地域においても課税要件を満たさない状況を意図的に創出する行為を指します。近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化やデジタル技術の発達と普及に伴い、多国籍企業による各国の税制および国際課税ルールの抜け穴(ループホール)を利用した実効税率の不当な引き下げ行為が顕在化し、国際的な政治問題(BEPS問題)として扱われるようになりました。
OECDにおけるBEPSプロジェクト
BEPSプロジェクトとは、近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化に伴い顕在化した、多国籍企業による各国の税制および国際課税ルールの抜け穴(ループホール)を利用した実効税率の不当な引き下げ、すなわち「税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)」問題に対処するため、経済協力開発機構(OECD)が、2012年(平成24年)に立ち上げた国際社会を巻き込んだ包括的議論のフレームワークのことです。
BEPS問題への有効な対処、並びに、国際課税ルールの再構築を目指し、BEPSプロジェクトではG20(財務大臣・中央銀行総裁会議)の要請に基づき策定された15項目の「BEPS行動計画」に沿って、国際協調による対応策の議論が進められました。その結果、2015年(平成27年)9月には、多くの行動計画に関する「最終報告書」が取りまとめられ、同年10月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議(ペルー・リマ)および11月のG20サミット(トルコ・アンタルヤ)に報告されました。
しかしながら、BEPSプロジェクトの中核的な議論である行動計画1「電子経済の課税上の課題への対処」については議論が長期化しました。その後、この課題に対する具体的な施策のフレームワークとして「Pillar One(第1の柱)」および「Pillar Two(第2の柱)」が整備されたものの、これらの導入・施行段階においては国際政治情勢の影響を受け、度々実施時期が延期される状況が続いています。現在、このPillar OneおよびPillar Twoが、国際社会における新たな課税ルールとして実質的に定着するかどうかが、国際税務の大きな注目点となっています。
なお、BEPS 行動計画1に関連する近時の動向や各国の動向については、別記事や国税庁のHP[1]にも更に詳細に掲載されていますのでご参照頂ければ幸いです。
[1] 国税庁HP「BEPSプロジェクト」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/beps/index.htm