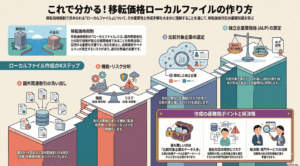トランプ政権の通商政策動向及び国際課税ルールへの影響【2025年1Q】

本記事では、2025年1月に発足した第2次米国トランプ政権の通商政策と国際課税ルールへの影響を理解するために、まずは共和党の基本的な国際租税方針と戦略の方向性を概観します。
従来から、共和党は国家主権と国内経済・産業の保護を重視し、国際租税協定やグローバルな税制改革に対して慎重な姿勢を取ることが多く、民主党(特にバイデン政権)の政策方針とは対極的な傾向にあります。第2次トランプ政権が発足したことにより、アメリカの通商政策と国際課税ルールに大きな変化が生じています。特に、OECDによるBEPS行動計画1(ピラー2)に基づくグローバル・ミニマム税率の導入提案に対しては、アメリカの租税権を侵害し、外国政府がアメリカ企業から利益を不当に抽出する可能性があるとして批判しています。
これらの政策転換は、国際的な課税ルールや各国の通商政策にも大きな影響を及ぼす可能性があります。アメリカがOECDの合意から離脱することで、国際課税の議論における調和化やコンセンサスの形成が難しくなり、多国籍企業の税務戦略にも再考が求められるでしょう。また、アメリカ独自の課税ルールの策定は、他国との通商交渉や経済関係にも影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
※本記事は2025年1月末時点の情報に基づいて記載しており、あくまでも筆者個人の見解が含まれている点につきご了承をお願いします。また、記事の内容に重要な影響を及ぼす新たな情報があれば適時記事の更新・修正を行っていく予定です。
米国共和党の国際租税方針と戦略の方向性
米国共和党の国際租税に関する考え方や方針は、主に国家主権と国内経済・産業の保護を重視する点に特徴があります。共和党は、国際租税協定やグローバルな税制改革に対して慎重な姿勢を取ることが多く、アメリカの財政的独立と競争力を維持することを優先します。日本製鉄によるUSスチールの買収案件に対して即座に政治介入があった点も記憶に新しい事例かと思います。
特に最近では、OECDによるBEPS行動計画1(ピラー2)によるグローバルミニマム税率の導入提案に対する反対表明が顕著です。この提案は、多国籍企業が利益を税率の低い国に移転することで各国の課税権や税収が浸食されることを防止するためのものですが、共和党はこれがアメリカの租税権を侵害し、外国政府がアメリカ企業から利益を不当に抽出する道を開くと批判しています
2024年9月17日付けのアメリカ合衆国下院から発出されたOECD事務局長宛の書簡では、共和党はバイデン政権がOECDとの協議を一方的に進めたことに強く反対し、「アメリカの税制主権を外国の手に委ねるべきではない」と明言しました。
共和党は、アメリカ国内で既に実施している「グローバル無形資産低課税所得(Global Intangible low-taxed income、以下「GILTI」という。)」制度(※1)を支持しており、これをグローバル的な最低税率導入に関する有効な代替と見なしています。GILTIは、アメリカの多国籍企業が海外で得た利益に対して一定の税率を課すことで、税逃れを防ぐ目的を持っています。共和党はこの制度が他国による不公平な競争やアメリカ企業への過度の負担を防ぐためのものとして、その維持を強く主張しています。
さらに、共和党は国際租税の文脈で中国を頻繁に引き合いに出し、中国が国家支援の下での不公正な競争を助長していると批判しています。OECDの提案するグローバルミニマム税率が中国のような国に利用されることで、アメリカの企業や労働者が不利益を被るとの懸念を強く示しています。
国内政策として、共和党は税制を通じてアメリカ企業が国際的に競争力を持つよう支援することに重点を置いています。これには、研究開発や低所得者向け住宅のための税控除など、アメリカのイノベーションと成長を支える国内保護政策的な税制措置が特色となっています。
以上を踏まえると、共和党の国際租税に対する基本方針としては、アメリカの経済的自立と国内産業・企業(特定の産業セクターに限られているとの見解もあります)の保護に焦点を当てたものであると言えます。また、国際租税の議論においても、共和党は自国の課税権の確保と国内経済の利益を最優先する姿勢を崩していません。つまり、2025年のトランプ政権誕生以降の米国の潮流としては、これまでのBEPSの議論における融和的姿勢を転換し、グローバルミニマム税率のような新たな国際課税ルールや制度を通じて米国企業が米国以外の税務管轄から課税を受けうる余地を基本的に拒絶する立場に変化してきているということになります。
バイデン政権(民主党)における租税戦略
では、それ以前の米国の民主党、特にバイデン政権下での国際租税に対するアプローチはどのようなものだったのでしょうか?
バイデン政権下の米国民主党は、グローバルな課税の公正性を向上させ、グルーバル企業による税逃れを防止することに重点を置いていました。バイデン政権は、国際的な協力を通じて税制の抜け穴(ループホール)を塞ぎ、多国籍企業による利益の移転を制限するための積極的な措置を支持していました。
例えば、2021年にバイデン政権が推進したアメリカンジョブプランやアメリカンファミリーズプランの文書には、国際租税改革の支持が明記されており、これらの計画を通じて国際税制の公正を高めるというバイデン政権の意向が示されています。これらの資料はホワイトハウスの公式ウェブサイトで公開されています。
バイデン政権がOECDと共同的歩調で進めていたグローバルミニマム税率の導入は、バイデン政権における特徴的な取り組みの一つで、この政策の主な目的は、法人税率の過度な引き下げ競争を抑え、各国が公平に税収を確保できるようにすることでした。バイデン政権は、グローバルミニマム税率が企業による税源ベースの侵食と利益移転の防止に役立つと考えており、2021年には130カ国以上がこの提案に合意したことが、新たな国際税務の潮流として世界中に大きく報道されました。
バイデン政権はまた、国内外の企業が公平に税負担を負うことを保証するための法改正にも取り組みました。具体的には、外国企業がアメリカ国内で事業を行う際に適正な税金を納めるよう求める措置や、アメリカ企業が海外で行う利益移転に対して最低税率を適用することなどが含まれます。これにより、租税基盤が侵食されるのを防ぎ、国内の公共サービスやインフラに必要な資金を確保することを主眼に置いていました。
バイデン政権下で提案された「アメリカンジョブプラン」や「アメリカンファミリーズプラン」などの経済政策も、これらの税制改革を通じて社会政策向けの資金を調達する計画が含まれています。これには、裕福な個人や大企業に対する税率の引き上げや、税逃れを防ぐための強化された監視と執行が含まれています。
このように、バイデン政権の国際租税に関する政策は、グローバルな課税の透明性と公正性を高めることに焦点を当て、国際社会との協調・協力を通じて税逃れを防止することに重きを置いており、OECDによるBEPSプロジェクトとも一部の議論を除けば協調的・協力的な側面が目立つものでもありました。民主党は、国内外からの税収を確保(企業による過度な課税逃れを防止)して、アメリカ国内での公共事業や社会福祉プログラムの資金源とする戦略ですので、その一環としてBEPSが提案する新たな国際課税ルールを容認する立場であったと言えます。
対照的に、共和党はこれらの国際租税上の提案に対して一貫して懸念を示しており、特にグローバルミニマム税率の導入には強く反対していました。彼らの批判は、こうした提案がアメリカの国家としての課税権を損なうとともに、外国政府がアメリカ企業から利益を抽出する手段になるというものでした。従って、2024年の大統領選挙で共和党が大勝し、第2次トランプ政権の誕生が確実となった時点で、従来の米国の国際課税政策が転換され、特に、OECDのBEPSプロジェクト(特に行動計画1のピラー1&2)に対して大きな逆風が吹くであろうことは十分予測されるものであったと言えます。
トランプ政権の通商政策動向及び国際課税ルールへの影響-2025-
第2次トランプ政権の誕生(復活)直後のホワイトハウスからいくつかのステートメントが公表されていますが、まずトランプ政権及び共和党の基本的な政策の方向性を理解するためには、手始めに2025年1月20日付け「President Trump’s America First Priorities」という題名のステートメントに軽く触れておく所から始めるのが良さそうです。
(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/)
このステートメントの具体的内容としては、バイデン政権のキャッチ&リリース政策の終了、メキシコにおける移民の待機政策の再開、壁の建設、非合法な国境越えへの亡命の終了、犯罪都市への対策強化、外国人の審査とスクリーニングの強化が行われます。また、アメリカの国境の安全を強化し、アメリカのコミュニティを守るための積極的な行動を含んでいます。最近のトランプ政権によるグリーンランドの購入やパナマ運河の返還に関する意思表明やコメントの数々もこの政策の一環なのかも知れません。
また、トランプ大統領は、エネルギー政策においてもアメリカのエネルギー支配を取り戻すための措置を実施するとしてします。これには、バイデン政権の気候過激主義政策の終了、許可プロセスの合理化、エネルギー生産と使用に不当な負担を課す規制の見直しが含まれます。また、パリ気候協定(COP)からの撤退も宣言しています。
そして、政府の組織・官僚制度を改革し、「スワンプ(沼)」の排除を目指すとしており、先日も米国内国歳入庁(IRS)を含む政府機関の大規模な人員削減計画が公表されています(IRSに関しては組織解体計画まであるとの報道もありましたが、これはさすがに国家の収入減を大きく損ないかねませんので実現は困難かとも思えます)。米国の政権交代時にはしばしば見られる話ではありますが、国際税務実務の現場では、実際に大なり小なり影響が及んでおり、税務調査や相互協議等の延期・中止と言った動きも見られます。
トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」政策における優先事項には、国際課税ルールや関税政策に関しても具体的な言及があります。アメリカはもはや外国の組織によって決定された国際課税ルールに従うことなく、アメリカのビジネスにペナルティや不利益を与えるような政策から解放されると宣言しています。こうした政策は、国内の経済活動を刺激し、アメリカの製造業を国際的な競争から守るための措置として位置づけられています。
次に、国際課税ルールに関する端的な政策表明の具体的事例としては、同じく2025年1月20日付けで公表されている「The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Tax Deal (Global Tax Deal)」という表題のステートメントがあります。直訳すると「経済協力開発機構(OECD)グローバル税制協定(グローバルタックスディール)」となりますね。表向きの形式は、米国財務長官・通商代表・OECD常駐代表宛のメモランダムですが、全世界向けに今後の米国の方針を発信したものと言えるでしょう。
以下、直訳ではありますが、内容としては、「前政権下で支持された OECD のグローバル税制は、米国の所得に対する域外管轄権を認めるだけでなく、米国の企業と労働者の利益にかなう税制を制定する米国の能力を制限する。グローバル税制やその他の差別的な外国税制慣行により、米国が外国税制の目的に従わない場合は、米国企業は報復的な国際税制に直面する可能性がある。この覚書は、グローバル税制が米国内で効力を持たないことを明確にすることで、米国の主権と経済競争力を取り戻す。」とあり、勝者が歴史を作ると言ったところでしょうか、前政権時代の議論の積み重ねはほぼなかったことになりそうです。
より具体的な内容は、下記の2つの項目にまとめられています。
第 1 項 グローバル税制協定の適用範囲
「財務長官および OECD の米国常駐代表は、前政権が米国に代わってグローバル税制協定に関して行ったいかなる約束も、議会がグローバル税制協定の関連条項を採択しない限り、米国内で効力を持たないことを OECD に通知するものとする。財務長官および米国通商代表は、この覚書の調査結果をその他の方法で実施するために、権限の範囲内で必要な追加措置をすべて講じるものとする。」
第 2 条 差別的および域外課税措置からの保護の選択肢
「財務長官は、米国通商代表部と協議の上、外国が米国との租税条約を遵守しているか、域外課税または米国企業に不釣り合いな影響を与える課税規則を実施しているか、実施する可能性があるかどうかを調査し、そのような不遵守または課税規則に対応して米国が採用または講じるべき保護措置またはその他の措置の選択肢のリストを作成し、大統領経済政策担当補佐官を通じて大統領に提出するものとする。財務長官は、調査結果および勧告を 60 日以内に大統領経済政策担当補佐官を通じて大統領に提出するものとする。」
となっており、このステートメントの公表日から60日以内となると2025年3月中には米国からOECD宛に何らかの調査結果報告が行われることになります(別途、当該ステートメントは予算承認後に実施されるとありますので解釈によって時期の前後はありそうですが)。調査内容次第では、日本も含め諸外国へのインパクトがそれなりに出てくる可能性もありますので、当面注目していきたい米国の動向のひとつになりそうです。
※1:グローバル無形資産低率課税所得(Global Intangible low-taxed income、以下「GILTI」という。)とは、一定の計算方法で算出したCFCの所得(GILTI所得)を米国株主側で合算課税する制度である。GILTI所得は、CFCの課税所得から適格事業資産投資(QBAI)の10%を差し引いた算定金額に、種々の調整を行い計算される。(なお、GILTI所得の50%部分は非課税の扱い。)また、CFCの課税所得に対して課された現地法人税は、合算課税を受けたGILTIに係る税額から、80%を上限に外国税額控除として控除することができる。
Conclusion & Summary(結論およびまとめ)
- トランプ政権の通商政策と国際課税ルールの変革は、アメリカ国内外の企業や経済に多大な影響を与えることが予想される。(関税政策は特に影響がありそうで、企業の移転価格対応にも影響が及ぶ可能性がある)
- アメリカがOECDのグローバル税制合意から離脱した場合、国際的な税制調和は揺らぎ、多国籍企業は改めて税務戦略の見直しを迫られる可能性がある。(特にBEPS AP1の2つのピラーに対する米国の意思決定の影響)
- また、米国トランプ政権下における通商政策のドラスティックな変化によって、アメリカと主要貿易相手国との関係も再び緊張する可能性がある。(対中国・カナダ・メキシコ・EUあたりとは既に始まっている)
- これらの変化に対応するため、多国籍企業は国際課税環境の変化を注視し、適切なリスクマネジメントを行う必要があるとともに、各国政府も新たな経済政策や税制改革を模索することが求められる。
- 今後当面は、アメリカの政策動向を継続的に追いながら、国際租税および通商の枠組みに対する影響や各国の反応をタイムリーにキャッチアップしつつ評価していくことが不可欠となる。