OECD移転価格ガイドラインには何が書かれているのか?(第4回)
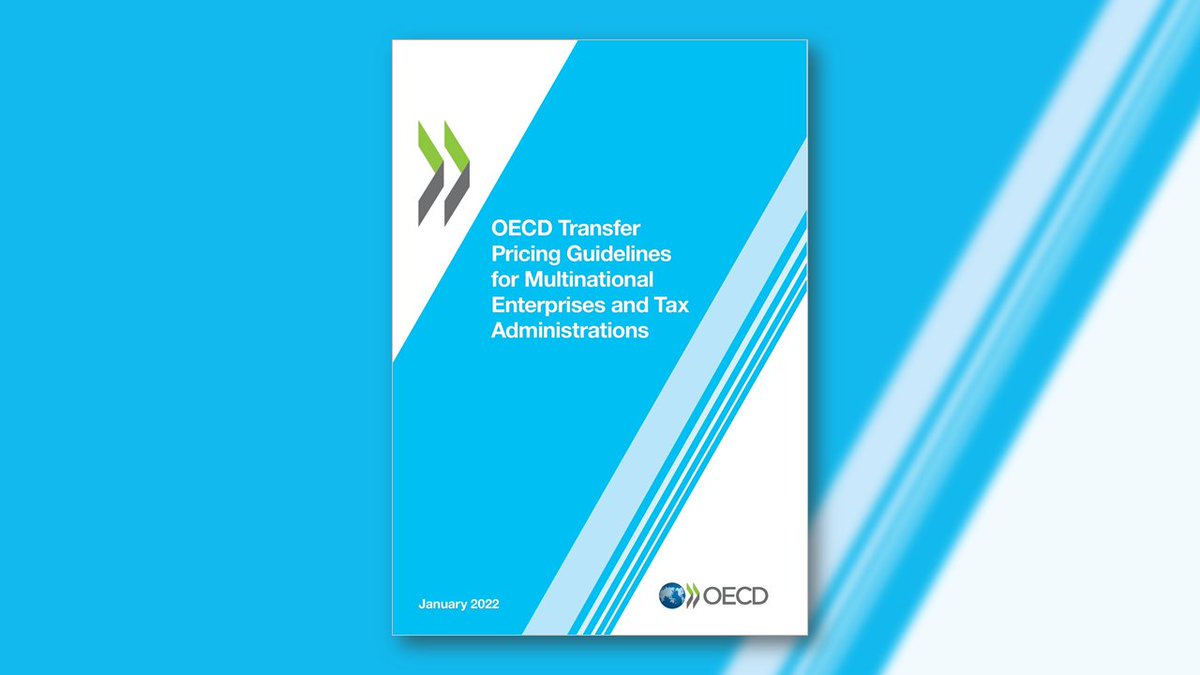
2017年7月10日に改訂版が公表されたOECD移転価格ガイドラインは、移転価格税制に携わる者としてはバイブル的な存在ですが、その内容の難解さとボリューム感が半端ないため、専門家やアドバイザーでも何が書かれているかざっくりとしか知らない方も多いのではないかと思います。
一方、全体をカバーして日本語訳および解説している書籍やWeb情報も現状(2018年3月末現在)存在していないようですし、LFの作成時に参考になるかもしれませんので、自分のコンサルティング業務向けの個人ノートでもあるのですが、作業当サイトの記事として順次公開していきます。
注)当サイトの記事に含まれる訳文や解説は、私見に基づいており、作業効率や時間短縮の観点から機械翻訳エンジンを用いている箇所があります。あくまでも参考訳としての扱いですので、正確な訳語や解釈については、原典または原文をご確認ください。
では、第4回ということで第1章:独立企業間原則のD節から続きを見ていくことにしましょう。
- D.独立企業原則の適用に関する指針
D.1. D.1. 商業・金融関係の特定
1.33
1.33 第二項1.6で述べたように、「比較可能性分析」は、独立企業原則のアプリケーションの中心である。独立企業原則の適用は、支配下の取引における条件と、当事者が独立し、比較可能な状況下で比較可能な取引を行った場合に行われたであろう条件との比較に基づく。このような分析には、2つの重要な側面がある。第一の側面は、関連企業間の商業上又は財務上の関係及びその関係に付随する条件及び経済的に関連する状況を特定することにより、支配下の取引を正確に描写すること、第二の側面は、支配下の取引の条件及び経済的に関連する状況を、独立企業間の同等の取引の条件及び経済的に関連する状況と正確に描写して比較することである。第I章のこのセクションは、関連企業間の商業上又は財務上の関係を特定し、統制された取引を正確に描写するためのガイダンスを提供する。この分析の第1の側面は、独立企業原則の下での当該支配下の取引の価格付けを検討する第2の側面とは異なる。第2章と第3章では、分析の第2の側面に関するガイダンスを提供する。本セクションの指針に基づき決定された支配下の取引に関する情報は、3.4項に示された比較可能性分析の典型的なプロセスのステップ2および3に特に関連している。
1.34
1.34 関連企業間の商業上又は財務上の関係を特定する典型的な処理及びその関係に付随する条件及び経済的に関連する事情は、多国籍企業グループが活動する産業部門(例えば、鉱業、医薬品、高級品等)及び当該部門で活動する事業の業績に影響を及ぼす要因について、広範な理解を必要とする。この理解は、多国籍企業グループがその事業戦略、市場、製品、サプライチェーン、遂行された主要な機能、使用された重要な資産、引き受けた重要なリスクなど、当該セクターのパフォーマンスに影響を与える要因にどのように対応しているかを概観した特定の多国籍企業グループの概要から導き出される。この情報は、第5章で述べたように、納税者の移転価格分析の裏付けとなるマスターファイルの一部として含まれる可能性が高く、多国籍企業グループの部材間の商業上又は財務上の関係を検討する上で有益な文脈を提供する。
1.35
1.35 その後、その多国籍企業グループ内の各多国籍企業がどのように活動しているかを特定し、各多国籍企業が何を行っているか(例えば、生産会社、販売会社)の分析を提供し、それらの間の取引で表されるように、関連企業との商業上または財務上の関係を特定する。実際の取引又は関連企業間の取引を正確に描写するには、取引の経済的に関連する特性の分析が必要である。これらの経済的関連性のある特徴は、取引の条件及び取引が行われる経済的関連性のある状況から成る。独立企業原則の適用は、比較可能な状況において比較可能な取引において独立当事者が合意したであろう条件を決定することに依存する。したがって、非統括取引との比較を行う前に、統括取引で表される商業関係または財務関係の経済的に関連のある特性を特定することが重要である。
1.36
1.36 実際の取引を正確に描写するために、関連企業間の商業上又は財務上の関係において特定される必要のある経済的関連性のある特性又は比較可能性の要因は、大別して以下のように分類することができる。
| 取引の契約条件(D.1.1) |
|---|
| 利用された資産と引き受けたリスクを考慮に入れて、取引の各当事者が遂行する機能。これには、当該機能が、当該当事者が属する多国籍企業グループによるより広範な価値の創出にどのように関連しているか、取引を取り巻く状況、業界慣行(D.1.2)が含まれる |
| 移転された財産又は提供された役務の特性(D.1.3) |
両当事者および両当事者が活動する市場の経済的状況(D.1.4) |
| 当事者が追求する事業戦略(D.1.5) |
1.36
実際の取引の経済的に関連する特性に関する情報は、第5章で述べたように、納税者によるその移転価格の分析を裏付けるために、ローカルファイルの一部として含めるべきである。
1.37
1.37 移転価格解析では、経済的に関連のある特性または比較可能性要因を、2つの独立したが関連したフェーズで使用する。第1フェーズは、この章の適用上、統制された取引を正確に描写する処理に関し、前段落に述べた区分に従って、取引の特徴(取引の条件、遂行された機能、使用された資産及び関連企業が引き受けたリスク、移転された製品又は提供されたサービスの特性、及び関連企業の状況を含む。)を確立することを含む。特定の取引において、上記にカテゴリーされた特性のいずれかが経済的に関連している範囲は、独立企業が同一の取引の条件を評価する際に、その取引が独立企業間で行われる場合にどの範囲会計されるかに依存する。
1.38
1.38 独立企業は、潜在的な取引の条件を評価する際に、その取引を現実的に利用可能な他の選択肢と比較し、商業目的を達成する明らかなより魅力的な機会を提供する選択肢がないと判断した場合にのみ取引を開始する。言い換えれば、独立企業は、次の最善の選択肢よりも悪い利益を得ることが期待されない場合にのみ、取引に参入することになる。例えば、ある企業が、他の潜在的顧客が同様の条件でより多くの支払いを行う意思があることを知っている場合、あるいは、より有益な条件で同じものを支払う意思があることを知っている場合、独立した商業企業が自社の製品に対して提供した価格を受け入れる可能性は低い。独立企業は、一般的に、それらのオプションを評価する際に、現実的に利用可能なオプション間の経済的に妥当な差異(リスク水準の差異など)を考慮する。したがって、取引の経済的に関連のある特性を特定することは、支配下の取引を正確に描写し、取引の当事者が考慮した特性の範囲を明らかにする上で不可欠であり、採用された取引よりも明らかに商業目的を達成するために現実的に利用可能な魅力的な機会がないという結論に達する。第三者が現実に利用可能なオプションの評価は、必ずしも単一の取引に限定されるものではなく、経済的に関連した取引のより広範な取り決めを考慮に入れることができるため、そのような評価を行う際には、取引のより広範な取り決めの文脈において取引を評価することが必要または有益であるかもしれない。、なぜなら、第三者が現実に利用可能なオプションの評価は、必ずしも単一の取引に限定されるものではなく、経済的に関連した取引のより広範な取り決めを考慮に入れることができるからである。
1.39
1.39 移転価格解析において経済的に関連する特性又は比較可能性の要因が用いられる第2段階は、支配下の取引の独立企業間価格を決定するために、支配下の取引と非支配下の取引を比較する第3章に定める手続きに関する。このような比較を行うために、納税者と税務当局は、まず、統制された取引の経済的に関連のある特性を特定する必要がある。第3章で述べたように、比較対象の状況と比較可能性を達成するためにどのような調整が必要かという比較可能性を確立する際には、統制された取決めと統制されていない取決めとの間の経済的に関連する特性の差異を考慮に入れる必要がある。
1.40
1.40 独立企業原則を適用するすべての方法は、独立企業が現実的に利用可能なオプションを検討し、あるオプションを他のオプションと比較する際に、その価値に重大な影響を与えるであろうオプション間の差異を考慮するという概念に結びつくことができる。例えば、ある一定の価格で製品を購入する前に、独立企業は通常、同等の条件で他者からより低い価格で同等の製品を購入できるかどうかを検討することが期待される。したがって、第II章第II部品で議論したように、同等の非管理価格法は、同様の非管理取引と比較し、当事者が管理取引に代わる市場に直接手を打っていたならば合意したであろう価格の直接的な見積りを提供する。しかしながら、独立企業間で課される価格に重大な影響を及ぼすこれらの非統制取引の特性のすべてが比較可能であるわけではない場合、当該方法は独立企業間取引の信頼性の低い代替手段となる。同様に、転売価格と原価加算方法は、統括取引で得られた総利益率と類似の非統括取引で得られた総利益率を比較する。この比較は、独立企業と同一の機能を果たしていれば、一方の当事者が得ることができたであろう総利益率の推定値を提供するものであり、したがって、一方の当事者が要求し、他方の当事者がそれらの機能を遂行するために独立の立場で支払うことを希望していたであろう支払額の推定値を提供するものである。第2章第3部で議論した他の方法は、独立企業と関連企業との間の純利益指標(利益率等)の比較に基づいており、独立企業とのみ取引した場合に各関連企業が得ることができたであろう利益、従って、当該企業が支配取引において自己のリソースを使用することに対して、当該企業が独立企業間で要求したであろう支払額を見積もるための手段である。比較に重大な影響を及ぼし得る状況の間に差異がある場合、比較の信頼性を向上させるために、可能な場合には、比較可能性の調整を行わなければならない。したがって、どのような場合でも、産業平均のリターンを調整しなければ、それ自体が独立企業間価格を確立することはできない。
1.41
1.41 特定の価格付け手法のアプリケーションにおけるこれらのファクターの妥当性についての議論については、第2章のそれらの手法の考察を参照されたい。






